2015-04-19
頑張らない
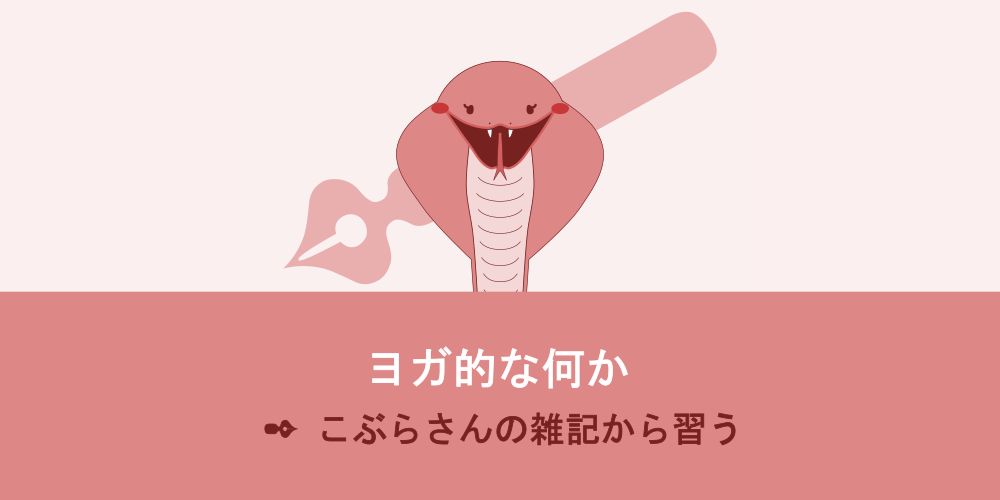
さてはて、「頑張らない」と目にして、どんな思考が走るでしょうか?
言葉の解釈の問題もあるので注意が必要なのですが、尾山ヨガ教室の授業では「頑張ることを止めましょう」と言います。ただしそれは、「努力をすることを止めましょう」ということではないと付け足します。つまりこれは、積極性を欠いた行為を促そうとしている訳ではありません。
「頑張る」のイメージ
しかし誤解を恐れずあえて「頑張ることを止めましょう」と言う理由の一つとしてまず、「頑張る」という言葉に、どのような映像(イメージ)が浮かぶかという問題があります。
- 眉間にぎゅっとシワを寄せる
- 奥歯をぎゅっと噛み締める
- 拳固をぎゅっと握り締める
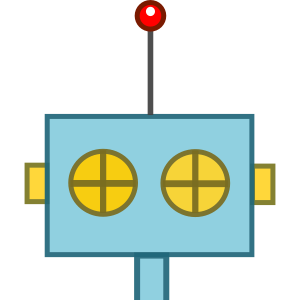
「頑張る」という言葉には「ぎゅっ」とするイメージ、つまり「リキム」というイメージが付いてくることがあるのです。
ですから、授業中に「リキムことを止めることを促す手段」として、「頑張らない」「頑張っていることに気づく」と声を大にして言うのです。(※ 例外もあります)
「頑張る」の意味
そして誤解を恐れずあえて「頑張ることを止めましょう」と言う理由の一つとして次に、「頑張る」という言葉に、どのような意味があるのかという問題があります。
【頑張る】 『goo辞書』より
- 困難にめげないで我慢してやり抜く。
- 自分の考え・意志をどこまでも通そうとする。我 (が) を張る。
- ある場所を占めて動かないでいる。
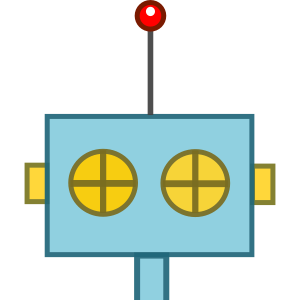
「頑張る」という言葉は、「我を張る」が転じたという説もあり、そこには「自分の意思を押し通す」という意味、「固着(執著)する」という意味があり、それはヨガの目的の反対側にあるのです。
ですから、授業中に「自分を押し通さないことを促す手段」として、「頑張らない」「頑張っていることに気づく」と声を大にして言うのです。
頑張らない
要するに、ヨガのしようとするところは、眉間にシワを寄せたり、肩肘を張ったり、踏ん張ったりしながら自分を押し通し、あるがままの事実に抵抗している自分に気付き、それを止めるところにあります。ハタヨガの体位とは、それら無意識的なリキミに気づく練習でもあるわけです。
そこに生じますのは、自分を押し通すことで得られる「満足感」という世俗的幸福感ではなく、自分を押し通すことを止めることで得られる「安心感」という修行的幸福感なのです。
ですから、授業中は「頑張れ・頑張れ」の世俗的価値観から脱する意味合いも込めて「頑張りませんように」と声を大にして言うのです。
頑張ってる感
頑張ってる感(リキム)があると力は流れません。というより力が停滞している場所に頑張ってる感(リキミ)が生じているからです。
∞∞∞∞∞∞ 力の流れの動画です ∞∞∞∞∞∞
1度目ー頑張ってる感あり
踏ん張りリキんで押しているため力(ベクトル)と力(ベクトル)が衝突し合っているようです。というより、押す力は相手の身体を通って床に流れているため、相手は床に頼ることができ姿勢を維持できるといえるでしょうか(ヨガマットごと相手が動く)。
2度目ー頑張ってる感なし
踏ん張らずリキまずに押しているため力(ベクトル)と力(ベクトル)が衝突せず流れているようです。というより、押す力が相手を通って床には流れないため、相手は床に頼ることができず姿勢を維持できないといえるでしょうか。
ーといいましても
自我(自分)は、「やってる感(頑張ってる感)」を感じたいというのも手伝って、リキみやすいです。そして自我は自分を通す(頑張る)ことが大好きです、というよりも自我は自分を押し通し、自分を満足させることにより存続しているのでしょうから、自我にとっては頑張らないことほど苦しいことはないのです。
「頑張らないなんてできるか!」と余計に自我がヘソを曲げるかもしれませんし、無理矢理に抑えつけていては、ただ自我が鬱屈するだけかもしれません。。。自我という心理的な力(ベクトル)を心理的な力(ベクトル)で止めようとすると、力と力が衝突し合うということです。
それでは修行は進みません。
ですから、肉体的にリキムことを止めることで自我という心理的な働きを止めることをするのです。そしてまた修行では、「礼拝(帰依)」という絶対的で巨大な力(ベクトル)を心理的に生み出すことにより、自我という心理的な働きを押し流し、力と力が衝突することを止めることをするのです。
動画の1度目は、自我と自我が衝突し合っている状態のようなものであり、2度目は自我が絶対に合流するような状態のようなものといえるでしょうか・・・?
頑張らない まとめ
- 肉体的には、リキまないこと。腑抜けないこと
- 心理的には、我を張らないこと(帰依すること)
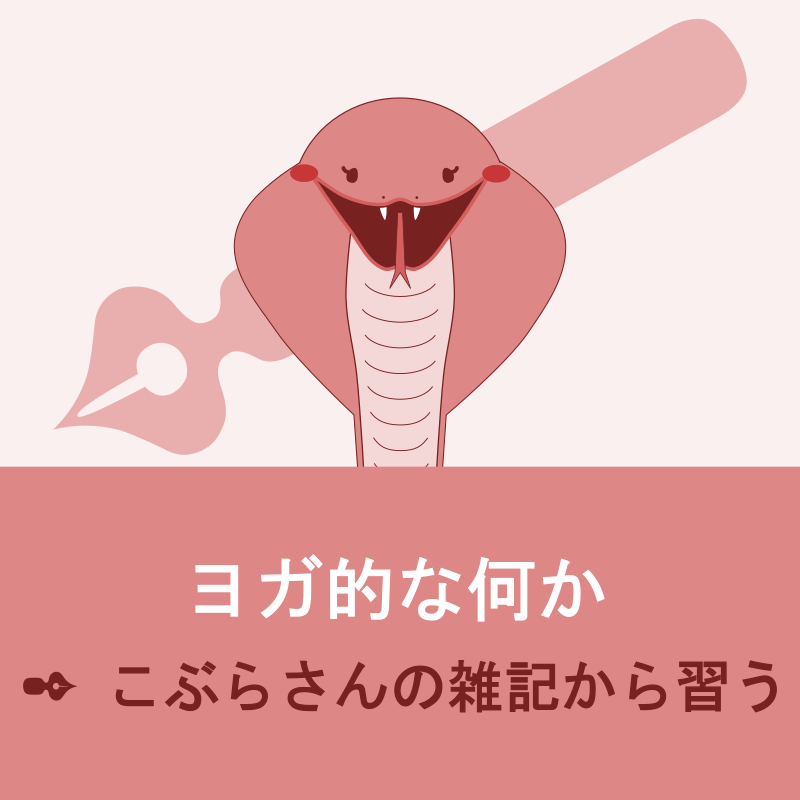 2015/05/18
2015/05/18